 大山町妻木にある国指定史跡の弥生時代集落遺跡。
大山町妻木にある国指定史跡の弥生時代集落遺跡。
以前にここらで案内を見て「麦パンダ??」と勝手に見間違えて行ってみたことあって、その時は今日よりもっと早朝で開いてなかった。「いつか行けたら、、」と思ってたので丁度イイ。(2009/3/21→)
ここは吉野ヶ里の四倍以上という広さの国内最大級の集落跡。どれだけ歩けるか(どのくらい時間かけちゃうか)分からないけど取り敢えず資料館「弥生の館むきばんだ」に入ってみた。
この「弥生の館」も無料の割にしっかりした展示で、個人的にはジオラマ模型が充実してて凄く良かった。
弥生時代の住居が種類別であり、原寸大もあり、当時の食料となった物の模型も並び、狩りや稲作風景のジオラマもあった。

個人で来てたっぽい人も多かったけど、夏休みシーズンだけに子供向けセミナーとかいろいろあるようで、ボランティアガイドさんには相手にされなかったけど(ひまそうなトコだと勧誘のように寄ってくるよね。ありがたいけど)親切な展示を見てるだけで何となく分かって問題なかった。
さてさて、外は結構気温が上がってたけど、せっかくなので少しは歩こうと帽子とタオルと水を持って進んでみた。
「弥生の館」の裏の広場からして広く長く、暑い夏には歩き甲斐がありそうだった。(案内図にはその先の眺め良さそうなトコまで「15分~20分」と書かれていた。。)
周りの森は蝉がけたたましく啼きまくっていて、さすがにウチの自宅の周り以上に啼いてて「森だ!」って感じがした。(ウチは神社の林並だからね)

でも、数分ほど歩くともう森の道を抜けて洞ノ原地区に出た。
ここは刈り込んだ丘の上の広場になってて、竪穴住居跡が木組み再現されてたりしていた。
そんな草原の中の住居跡を見ながらゆっくり歩いた。

そして先の方の一軒は再現されていて家の中にも入れた。
意外と明るく、風通し良く涼しかった。これは夏でも暮らせそうだわ。
でも昼間は毎日、丘の下の田畑での稲作や森や海などの狩りに一斉に出勤してたそうで、集落は夕方からの寝床メインだったようだ。
弥生の昔から通勤とかあったんだ。。日本人の生活のリズムは古代から変わってないのかもね。。
そして住居跡の先には墳墓群。
石で囲まれた四角の角を引っぱった形をしてて、ああ「むきばんだ」の顔みたいなマークはこの形をモチーフにしてるんだと気付いた。

芝生ではバッタが波のように飛び回ってたし、日当たりいいけどキノコなんかも生えてたりして豊かな土地って感じだった。
そして墳墓の先はいい眺めの展望スポット。
これはスゴイ。
開けた山から広く眺め下ろせる淀江平野と米子方面の町、青い日本海の先に島根半島の山が霞んでた。
風も心地よくしばらくのんびりと眺望を楽しんだ。

丘の先に高床の建物が見えた。あそこまでが洞ノ原地区で夕陽がきれいなスポットだそうだけど、夕方じゃないから下りて行くつもりは無し。眺めは此処で充分。
そのもっと先にあった櫓のような展望台は「伯耆古代の丘公園」
有料のレジャー的な公園?目の前にこんな眺めのいい史跡があるのに?とか思った。
そしてとても懐かしいシンプルなカラーのキハ(気動車)が二両編成で通ってた。あれは山陰本線?
海には船も見え、のどかな風景も意外と動きが有って眺めてて飽きなかった。
そして来た道を戻った。
「弥生の館」までもどって、そういえば何か食べるとこはないんだっけ?とかもう一度覗いて(なかった)
取り敢えずこんなもんかな、、、と思ったけど、やっぱ少し気になって、反対側の妻木山地区にも歩いてみた。
ら、こっちの方が再現された竪穴住居が沢山並んでいた。
なんでも、150棟以上の住居跡と200棟以上の倉庫跡が発掘された区域で集落の中心街だったようだ。

住居もさっき入ったものより大型のが多く、その全棟解放されてて中に入れるので、とりあえずひとつ入ってみた。
子沢山でも住めそうな広さで、中二階のロフトっぽい棚とかあったりしてなんか充実してそうだった。
こっちも東側の展望が少し開けてたけどやっぱ眺望はさっきの洞ノ原地区(そっちが晩田山なのかな)には全然及ばなかった。
これでも全体の三分の一くらいみたいだけどもう満腹。汗かいたし。
「弥生の館」にまた戻って館内の空調で落ち着いてから車に戻った。
 大山町名和の山陰道名和ICと9号の間にある道の駅。
大山町名和の山陰道名和ICと9号の間にある道の駅。 でも、食堂部は9時半からみたいで、ソフトや御当地バーガーはゲット出来なかった。。
でも、食堂部は9時半からみたいで、ソフトや御当地バーガーはゲット出来なかった。。
 鳥取市気高町浜村の9号沿いにある撮影スポット休憩駐車場。
鳥取市気高町浜村の9号沿いにある撮影スポット休憩駐車場。
 鯖江市三六町にある鉄板焼菓子店。
鯖江市三六町にある鉄板焼菓子店。 ってわけで、無事に「サラダ焼き」をゲット!
ってわけで、無事に「サラダ焼き」をゲット!
 大野市天神町にある水汲場。
大野市天神町にある水汲場。
 ってわけで車内に転がってた空きPET500ml二本に水を汲んでドライブの供とした。
ってわけで車内に転がってた空きPET500ml二本に水を汲んでドライブの供とした。 大野市朝日の158号沿いにある道の駅。
大野市朝日の158号沿いにある道の駅。 トイレでスッキリ。
トイレでスッキリ。
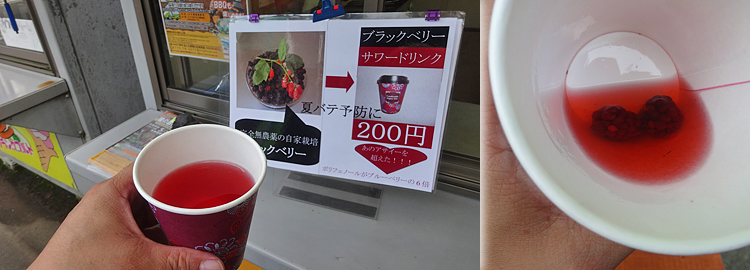
 高山市荘川町中畑の158号沿いにある蕎麦店。
高山市荘川町中畑の158号沿いにある蕎麦店。 それが、今日は駐車場も空いててガラガラ。
それが、今日は駐車場も空いててガラガラ。
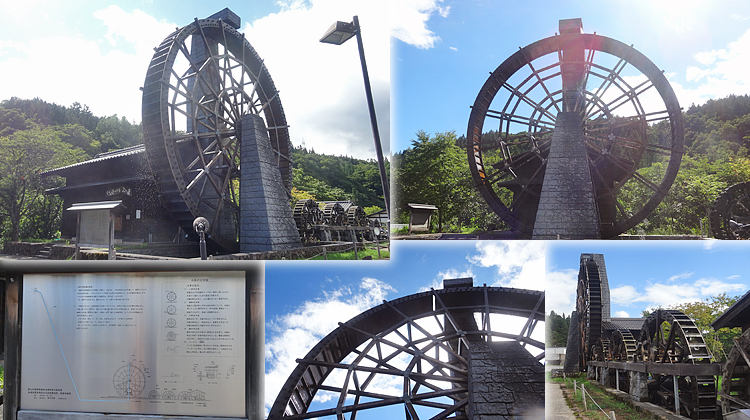
 高山市荘川町六廐の六廐川にある滝。
高山市荘川町六廐の六廐川にある滝。


 下仁田町南野牧の254号沿いにある食堂。
下仁田町南野牧の254号沿いにある食堂。

 結城市結城の50号沿いにある「旅の駅」認定ドライブイン。
結城市結城の50号沿いにある「旅の駅」認定ドライブイン。
 食後は少し売場の方も見てみた。
食後は少し売場の方も見てみた。 幟が出てて気になってた茨城のソウルフード「干しいも」は、土産売場ではなんか小さいコーナーながら贅沢品のようなお値段で売られてた。
幟が出てて気になってた茨城のソウルフード「干しいも」は、土産売場ではなんか小さいコーナーながら贅沢品のようなお値段で売られてた。