 三島市大宮町にある神社。
三島市大宮町にある神社。
伊豆国の一宮にして総社の官幣大社。
具体的に去年くらいから来たいと思っててやっと来れた感じだけど、いざ来てみると何が目的で何ネタで来たかったのか思い出せなくて困った。
さて石鳥居をくぐって(ないけど)中に入ると、お祭り屋台が設営されていた。普通に屋台が並んでる神社なのかな?桜祭りとかあるのかな?
そしたら「たたり石」なんてものが屋台のシートに凭れ掛られてて、えーいいの?大丈夫なの?とか思ったけど、説明読んだら元々「たたり(絡垜)」はもつれを防いで整理するという意味だそうで、神社前の道の流れを整理するものだったそうだ。だからまぁいいのかな。。
「安達藤九郎盛長警護の跡」というのも隠れるようにあった。(名のある松の木かと思ったらそうでは無かった)源家再興を祈願しに何度も参拝した源頼朝を警護した場所だそうだ。

そこから小さな橋のある参道は両側に神池という池があった。湧き水とか伏流水とか透き通った池かと思いきや、水はキレイではなく普通の錦鯉の泳ぐ公園的な池だった。
でも参道の枝垂れ桜がチラホラ咲き始めてたのでそれはそれでいい感じ。(神社のサイトを見ると満開の時に池に落ちた花びらが一面覆ってキレイなようだ)
総門をくぐって、縁起餅の福太郎の販売テントを見つつ神門に進んで境内に入った。
総門は伊豆大震災後の昭和6年(1931)の建替え、神門は慶応3年(1865)。この神社は殆どの建物が嘉永7年(1854)の東海大地震で倒壊したので幕末のものが多いようだ。

境内中央には拝殿ではなく舞殿というのがあった。
横を見ると天然記念物という金木犀、樹齢1200年だそうだ。樹木は地震を乗り越えたのね。
平安時代?ってことは頼朝も見てるのかな?花は夏の終わりだそうだ。あー咲いてる頃に来たかったなぁ。
社殿は慶応2年(1866)完成の重要文化財。大きくて立派。飾りは少ないけど彫刻もあって本殿も立派だった。

境内を見てまわって、舞殿の旧大鬼も見て神門を出た。
あとは神馬舎には馬の像、その隣に源頼朝と北条政子の腰かけ石なんてのもあった。これはちょっと作っちゃった感あって疑わしく思えた。(だってものすごくイスっぽいんだもの)
そして芸能殿という旧総門とされるものの先の奥に「神鹿園」というシカの柵があった。
あーこれだこれだ、思い出した。去年行った弥彦神社の鹿が春日大社とこの三嶋大社から譲り受けた鹿だったと知って、鹿つながりでそういえば行ったことなかった此処が気になってたんだっけ。(よかった、、実は池が目的だったかもと思って少々落胆してたトコだった)

鹿は沢山いたけどみんなグデーっとしてた。ん?まだ冬眠時期?月曜の朝だから?神社の鹿はだいたい何処でもシャキッとしてる印象で、ここまであからさまにかったるそうな鹿たちは初めて見たかも。。寝てるような烏骨鶏もいた。いや、ニワトリ系は朝は元気にしてろよw
ゲージの外でちょんちょん跳ねてたツグミは元気いっぱいだった。(写真で見たらシロハラのようだった)
あとは表に戻って、宝物殿という新しい建物の脇に湧水の井っぽい「御神泉」というのがあった。些とオブジェっぽいけど水は清らかで苔生した石もイイ感じ。表の池もこのくらいの清らかさがほしかった。。
この日の日誌→
タグ:観:宮 観:石 観:池 観:門 観:然 観:重 観:水 植:樹 植:花 動:鳥 動:獣
 富士吉田市下吉田にあるうどん店。
富士吉田市下吉田にあるうどん店。
 富士河口湖町精進の精進湖前の県道沿いにある駐車場。
富士河口湖町精進の精進湖前の県道沿いにある駐車場。

 富士市比奈にある公園。
富士市比奈にある公園。



 三島市大宮町にある神社。
三島市大宮町にある神社。



 伊東市湯川の135号沿いにある道の駅。
伊東市湯川の135号沿いにある道の駅。
 でもメニュー見てて「元祖名物」とあった揚げ干物120円が気になった。この店はひもの屋の直営店だそうで間違いなさそうだったので二人で追加。
でもメニュー見てて「元祖名物」とあった揚げ干物120円が気になった。この店はひもの屋の直営店だそうで間違いなさそうだったので二人で追加。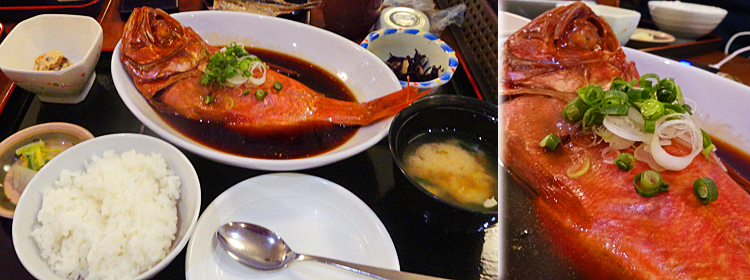
 伊東市岡にある競輪場。
伊東市岡にある競輪場。



 熱海市熱海滝知山の有料道路伊豆スカイラインにある展望駐車場。
熱海市熱海滝知山の有料道路伊豆スカイラインにある展望駐車場。

 静岡市清水区八木間町の52号沿いにあるラーメン店。
静岡市清水区八木間町の52号沿いにあるラーメン店。

 湖西市白須賀の1号沿いにある道の駅。
湖西市白須賀の1号沿いにある道の駅。 が、外にあったスナックコーナーがスッキリなくなってて驚いた。
が、外にあったスナックコーナーがスッキリなくなってて驚いた。
 席は窓に向いたカウンター席だったから海と1号バイパスをのんびり眺められた。
席は窓に向いたカウンター席だったから海と1号バイパスをのんびり眺められた。 西尾市小島町岡ノ山の23号沿いにある道の駅。
西尾市小島町岡ノ山の23号沿いにある道の駅。 で、店内を見てまわったら、面白そうなのあった。
で、店内を見てまわったら、面白そうなのあった。
 ペロリと食べ終えて落ち着いてみて、やっぱり眠気あったのでそのままシート倒さずに仮眠した。(倒すとガッツリ寝ちゃいそうなので)
ペロリと食べ終えて落ち着いてみて、やっぱり眠気あったのでそのままシート倒さずに仮眠した。(倒すとガッツリ寝ちゃいそうなので)