 相模原市緑区太井の413号沿いにある公園。
相模原市緑区太井の413号沿いにある公園。
ここは何度も通ってて見かけて知ってたけど一度も寄ったことが無かった。市街から近いから駐車場有料でもおかしくないくらいだけど料金の表記は無いから無料だとは思ってた。まぁいつも帰りで余裕なかったからかな。今日は早いので寄ってみた。
城山ダムの西の津久井湖の南側のこのエリアが「花の苑地」、湖対岸の北側が「水の苑地」、そして城跡のエリアと山の裏にも駐車場あって広場のあるエリアの広い公園だそうだ。
眺め下ろす津久井湖は、中学生の頃にバス釣りに来たことある湖。何度かヒットしつつ何度もバラしちゃって難しかったけど楽しめた好印象のダム湖だった。まぁヘタクソだったからねぇ。

公園のメインは津久井城跡。国道向かいの山。これかぁ。これはさすがに時間に余裕があるとはいえ今から登る気にはならないなぁ。ひざいたいし。
津久井城は鎌倉時代の築城だけど整備されたのは戦国時代で北条の城だったそうだ。
花壇の花をみながら津久井湖観光センターに歩いた。

観光センターは昭和チックな売店だった。割と地域の物をいろいろと売ってたけど特に何も買わなかった。それより入口にダムカードの貼紙があったのでここでもらえるものかと会計のとこで聞いてみたら、それは「水の苑地」の方にあるダム管理事務所での配布だそうだ。。あーっそ。
あとはフラフラと「ガーデンテラス」に歩いてみた。

咲いてたのはハーブ系の小さな花とかだったけど、ギンヨウアカシア?のサラサラした葉に小さい粒のような花とかいい感じだった。(花咲く前のつぼみだったのかも)
城山と湖と花の眺めで落ち着く、軽い休憩にちょうどいいトコだった。
この日の日誌→
 道志村の413号沿いにある道の駅。
道志村の413号沿いにある道の駅。
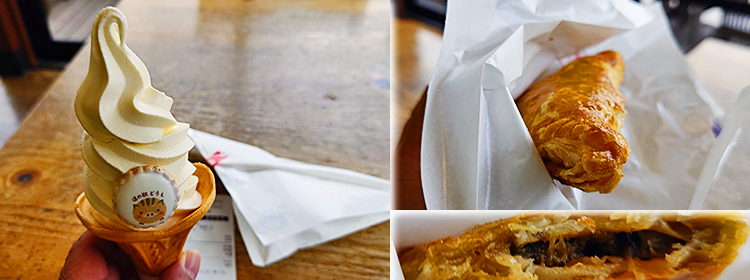

 富士吉田市下吉田にあるうどん店。
富士吉田市下吉田にあるうどん店。
 富士河口湖町精進の精進湖前の県道沿いにある駐車場。
富士河口湖町精進の精進湖前の県道沿いにある駐車場。

 富士市比奈にある公園。
富士市比奈にある公園。



 三島市大宮町にある神社。
三島市大宮町にある神社。


