 沼田市西倉内町にある公園。公園全域が沼田城跡。
沼田市西倉内町にある公園。公園全域が沼田城跡。
トイレ休憩のつもりでもあったけど、沼田城跡ということで以前から来てみたいとは思っていた公園だった。
まず入口の無料駐車場には「三之丸跡」とあった。
市民の憩いの広場的な公園だと「城跡」というのはさり気なく掲げるだけの所とかも多いけど、ここは沼田城跡という碑と案内版があちこちにあり、「真田街道」という(再来年の大河ドラマのPR)幟も並んでいた。
この城は関東入口の要所に在った為、上杉、北条、武田(真田)で取りあって、最後は徳川天領になって城郭を破却、御殿のみ再建して明治で廃城。だそうだ。
公園の案内図を見つつ取り敢えず園内に歩くと、いきなり「本丸跡」だった。あれ?二の丸は?
「本丸跡」は中央に花壇のある広場で赤紫の花(センニチコウ)がキレイに咲いていた。
そして奥の方には黒い鐘楼があった。??本丸に鐘楼?
説明を読むと、、鐘櫓は真田時代の城内にあったけど廃城で取り壊し、後の明治期に沼田町役場に建てた鐘楼を修復の際に保存してた城鐘に替えて昭和中期まで市民に親しまれたそうな。(その城鐘は公民館で展示、ここに吊られてるのは城鐘に替える前の梵鐘だそうだ)
つまりこれは旧市内にあった明治期デザインの鐘楼堂の復元。城跡とはチグハグだけどよくある光景。(笠間城跡でも見た)

鐘楼の反対側は「利根英霊殿」という神社があって、その辺りに五層の天守があったそうな。
低い丘にはなってたけど天守台はなかった。
まぁね幕府により「城郭を破却」じゃあ天守と天守台なんか真っ先に取り壊すよね。
その脇には飼育小屋が並んでて何がいるのかと覗くと、インコ、烏骨鶏、鳩、孔雀、兎とかの身近?な小動物だったけど、インコとウサギは数が多くにぎやか。特にインコはごちゃまんといてうるさいくらいだった。
(ウサギはもふもふで見てると固まっちゃうからあまりみないようにした)
そして本丸跡の一番奥が「西櫓台」
ここは破却時に埋め固めた部分だったそうで公園整備で発掘されたそうだ。
その櫓台の上には樹齢推定400年の「御殿桜」。この一画だけが往時の沼田城の遺構の残った場所で、絵図と年表が立っていた。
桜咲いてるの見てみたいけど、そんな時期には車停められないよね。

石段、石垣には柵あって入れず、櫓台も桜の保全で立ち入らないようにとあったので、この裏の石垣を見れなかった。(後で裏から回ろうかと思ってて忘れてた)
本丸から北に進むと「捨曲輪跡」という木漏れ日爽やかな林の広場になってた。捨曲輪ってなんだ?(沼田城初期の本丸らしい)
奥の中心部に「平八石」というのがあった。
城を築いた沼田顕泰の子の沼田平八郎景義という猛将を謀殺して首級を載せた石だそうだ。。
祟ったんだろうね、、それで捨曲輪なのかね。

この城(公園)は崖っぷちの割に木々が茂って思いのほかあまり展望きかないなかで、この捨曲輪の縁が一番展望よく見えた。
北西部の山々と月夜野方面の町並みが見渡せて、お弁当食べてる親子とかいた。
捨曲輪の東側にあった「天狗堂」を覗きつつ、元天守台の丘の裏から東に抜けた。
公園のほぼ中央の天守跡前には国重文「旧生方家住宅」があった。
町中にあった沼田藩薬種御用達商家の江戸中期築の町屋だそうで、東日本で最も古い城下町の本格的町家だとか。
有料だったけど100円だったから入ってみた。

町屋だから両隣にも家が並んでたため建物の横には窓も何もなく、
屋敷は奥に縦に長く暗く続いてた。
その奥のお勝手の土間には、なんと(なぜか)沼田城のジオラマと沼田城五層天守の模型があった!
そうそうこれ、ネットで見かけてたから何処かにある筈だとは思ってたけど、公園内に資料館とかそれらしいのがなかったから、別の場所かと諦めてたけど、まさかこんなトコにあるとは、、入って良かった。

それにしてもやっぱ五層は立派な天守。
これ、残ってたら松本城以上の観光名所になるよね。
立派すぎるから幕府から睨まれちゃったんじゃないか?
取り壊すくらいなら、焼失した江戸城の代わりに江戸に移築すれば良かったのにねー、勿体ない。
ところでこの「旧生方家住宅」
天守模型のある台所は勝手口が開いて光はいるけど、内側に五つ並ぶ部屋は天井高いのに暗くて閉鎖的。
一番奥の五の間にある「ぬりごめ壁」の解説には「寒気を防ぐためと嫁・使用人の逃亡防止……住居よりむしろ牢獄を連想する」などと書かれておりゾッとした。
 この「旧生方家住宅」の先から広いグランドまでが「二の丸跡」らしい。
この「旧生方家住宅」の先から広いグランドまでが「二の丸跡」らしい。
そういえば来たときからグランドから場内放送が聞こえてたりしててイベントやってそうな感じだったので、最後に覗いて見てみたら消防車がずらっと並んでて壮観だった。これは見せ物ではなく消防団の「ポンプ操法競技大会」だった。
脇のテニスコートの手前には「本丸堀跡」があった。
ここの石垣も当時の物だそうだ。
見える堀はホンの一部で、天守の前と二の丸の間も深い堀だったそうだから「旧生方家住宅」のあたりは埋め立てられた堀の跡らしい。いろいろ埋まってそうだねぇ。
取り壊された城跡の割には思いのほか遺構が残ってて、いろいろ見所あってイイ城跡公園だった。
再来年の大河ドラマは真田幸村。この沼田城は幸村の兄の信之の城だからドラマには出てくるかなぁ?
タグ:観:城 観:楼 植:花 動:獣 楽:眺 観:石 観:屋 観:重 観:模
 邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。
邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。
 佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。
佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。

 館林市大手町にあるたい焼きのお店。
館林市大手町にあるたい焼きのお店。 たい焼きは一匹100円。
たい焼きは一匹100円。 少しして踏切でつかまって止まったトコで包みを開いてみた。
少しして踏切でつかまって止まったトコで包みを開いてみた。


 ら、県道の大きな鳥居の先はずっと坂道。
ら、県道の大きな鳥居の先はずっと坂道。

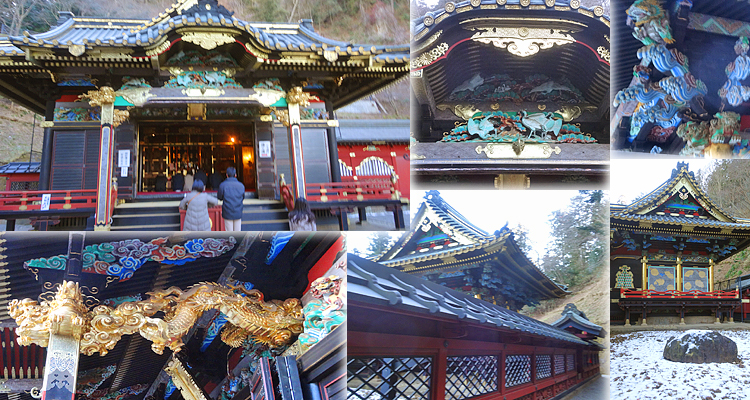
 ゆっくり一回りして下る。
ゆっくり一回りして下る。
 で、来てみたら山のかけ上がりにあるお寺だったけど、坂の上の本堂の裏に駐車場があるので下から登らずに済んで楽々だった。ありがたい。(下にも駐車場があるのでちゃんと参拝する人は登った方がいいのかもね)
で、来てみたら山のかけ上がりにあるお寺だったけど、坂の上の本堂の裏に駐車場があるので下から登らずに済んで楽々だった。ありがたい。(下にも駐車場があるのでちゃんと参拝する人は登った方がいいのかもね) その横の丸いだるま型の絵馬が吊されていた建物(寺務所?)の端には大きなだるまが置かれてて、「達磨堂」というダルマのコレクションルームになっていた。
その横の丸いだるま型の絵馬が吊されていた建物(寺務所?)の端には大きなだるまが置かれてて、「達磨堂」というダルマのコレクションルームになっていた。
 入口に達磨寺の歴史や達磨大師についてても書かれてた。
入口に達磨寺の歴史や達磨大師についてても書かれてた。 伊勢崎市富塚町の462号沿いにある自販機店。
伊勢崎市富塚町の462号沿いにある自販機店。


 桐生市相生町にあるオリジナル商品「コロリンシュウマイ」専門店。
桐生市相生町にあるオリジナル商品「コロリンシュウマイ」専門店。 少し値上げしたそうだけど5個150円は全然文句ない値段。っていうかもっと払いたいくらい。
少し値上げしたそうだけど5個150円は全然文句ない値段。っていうかもっと払いたいくらい。
 沼田市上之町の120号沿いにある焼きまんぢゅうの店。
沼田市上之町の120号沿いにある焼きまんぢゅうの店。
 沼田市西倉内町にある公園。公園全域が沼田城跡。
沼田市西倉内町にある公園。公園全域が沼田城跡。




 この「旧生方家住宅」の先から広いグランドまでが「二の丸跡」らしい。
この「旧生方家住宅」の先から広いグランドまでが「二の丸跡」らしい。 桐生市黒保根町下田沢の122号沿いにある道の駅。
桐生市黒保根町下田沢の122号沿いにある道の駅。 中は結構広く、半分手前はスナックコーナー+休憩的な自由な感じで、奥半分が食堂になってた。
中は結構広く、半分手前はスナックコーナー+休憩的な自由な感じで、奥半分が食堂になってた。
 太田市強戸町にある焼きそば店。
太田市強戸町にある焼きそば店。